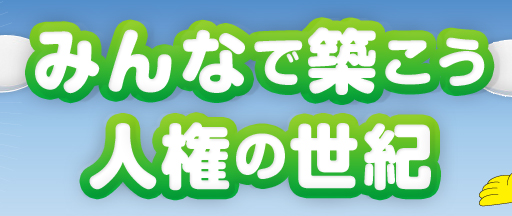
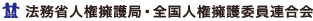
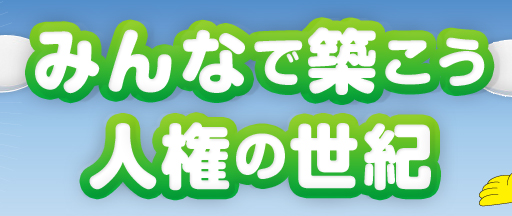

企業は組織内外の多くの人が関わりあって成り立っています。また、地域は多くの人が共存して成り立っています。組織内や地域内において、一人一人の違いを認め、それぞれの視点や能力を豊かさとして生かすことこそが、人権が尊重される職場や地域づくりにつながります。
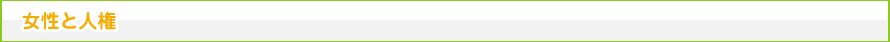
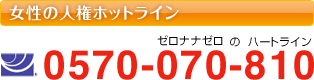
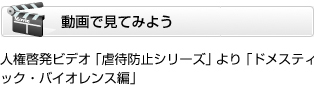
男女平等の理念は、日本国憲法に明記されており、法制上も男女平等の原則が確立されています。しかし、今でも、「男は仕事、女は家庭」といった男女の役割を固定的に捉える意識が社会に根強く残っており、このことが職場や地域において様々な男女差別を生む原因となっています。
現在、働く女性は全就業者の4割を超えていますが、仕事と子育てが両立できる環境が整っていないことなどから、男女間には勤続年数や賃金の面で格差があらわれています。男性を含めた働き方の見直しを図り、家庭と仕事の両立支援体制を充実させ、全ての人が性別にとらわれることなく、その個性と能力を十分に発揮できる社会の実現が求められています。
また、性犯罪等の女性に対する暴力や、夫・パートナーからの暴力(ドメスティック・バイオレンス)、職場におけるセクシュアル・ハラスメント、つきまとい・ストーカー行為等も、女性の人権に関わる重大な問題です。法務省の人権擁護機関では、専用相談電話「女性の人権ホットライン」を設置し、人権擁護委員や法務局職員が様々な人権問題に関する相談に応じています。
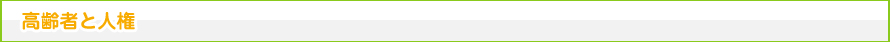
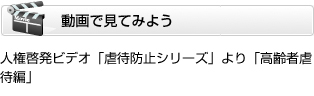
我が国の高齢化は今後も進み、総務省の統計によれば、既に平成25年9月には、国民の4人に1人が65歳以上になったと推計されています。高齢社会を活力ある社会とするためには、年齢に関わりなく働き続けることができる環境を整えることが必要ですが、実際には、年齢を理由に就業や社会的活動への参加を制限されることが少なくありません。
高齢者には、長年培ってきた豊富な経験や知識、優れた技術があり、これは企業にとって大きな財産です。これをいかせるよう、年齢にかかわらず誰もが働きやすい環境作りを進めることは、今後の企業発展のために必要ではないでしょうか。
一方、高齢者に対しては、家族や介護者等による身体的・心理的虐待や、介護・世話の放棄(ネグレクト)、家族等による年金、預貯金等の無断引き出し、処分(経済的虐待)などといった人権侵害も大きな社会問題となっています。
こうした問題の背景には、高齢者の尊厳を軽視する考え方や態度があるのではないでしょうか。高齢者が生き生きと暮らせる社会の実現を目指して、高齢者についての理解を深め、高齢者を大切にする心を育てる必要があります。
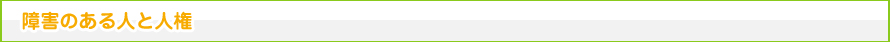
現在、我が国の障害のある人の数は約741万人で、およそ国民の6%が何らかの障害を持っていることとなり、障害のある人が決して特別な存在ではないことが分かります。
我が国では、「障害のある人も地域の中で普通の暮らしができる社会に」というノーマライゼーションを基本理念の一つとし、障害者基本法の改正、障害者基本計画の策定などの施策を進めてきました。
しかし、現実には、車椅子での乗車やアパートへの入居を拒否される事案が発生するなど、障害のある人の自立が阻まれることもあります。障害のある人を含む全ての人々にとって住みよい平等な地域社会をつくるために、全ての人々が障害のある人について十分に理解し、必要な配慮をすることが求められています。
一方、障害のある人の社会参加は、十分に進んでいるとは言えない状況にあります。
一定規模以上の企業には、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、一定の割合で障害のある人を雇用することが義務付けられていますが、この法定雇用率を達成した企業は半分にも満たない状況が続いています。
合理的な配慮や支援を受けることで、障害のある人も、働いて収入を得る、自らの能力を発揮して自己実現を図ることができる環境の実現が求められています。
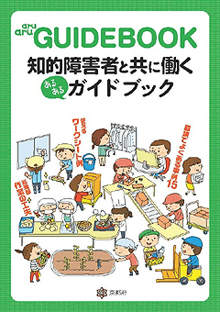
[参考資料の御紹介]
平成25年度人権啓発資料法務大臣表彰最優秀賞
「知的障害者と共に働くあるあるガイドブック」(京都府作成)
本ガイドブックは、障害のある人と共に働くという視点から企画・構成され、障害のある人も快適に働ける職場づくりのガイドラインが具体的に明示されています。
誰にでも理解できる分かりやすいハンドブックとして、障害のある人の雇用促進にも貢献できる内容であり、また、人権啓発の観点からも極めて効果的であることから、平成25年度人権啓発資料法務大臣表彰において最優秀賞を受賞しました。下記のリンクより御覧いただけますので、あわせて御参照ください。
■ 問合せ先
京都府 商工労働観光部総合就業支援室
住所:〒601-8047 京都府京都市南区東九条下殿田町70京都テルサ東館1階
電話:075-682-8918
URL:http://www.pref.kyoto.jp/jobpark/h-guide1.html
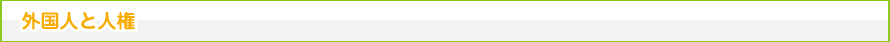
我が国に入国する外国人は長期的には増える傾向にあり、国内でも多くの外国人が生活・就労しています。
そして、言語、宗教、習慣等の違いから、外国人をめぐって様々な人権問題が発生しています。例えば、外国人であることを理由に、アパートへの入居や公衆浴場での入浴を拒否されたり、外国人を排斥する趣旨の言動が公然とされるという事案が発生しています。
また、外国人を安価な労働力と見なす傾向は根強く残っており、外国人労働者が日本人と比べて不利な条件で雇用されているケースが少なくありません。我が国では、法制上、国籍による労働者の差別は禁止されています。国内で働く限り、日本人・外国人に関係なく、同じ労働法が適用されます。
地域においても企業においても、外国人の生活習慣等を理解・尊重し、文化等の多様性を認めるとともに、偏見や差別をなくしていく必要があります。国籍、民族、言語、文化、習慣等、様々な違いを個性としていかせる社会を目指していく必要があるのではないでしょうか。
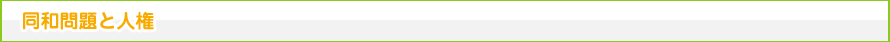
同和問題は、日本社会の歴史的過程で形づくられた身分差別により、日本国民の一部の人々が、長い間、経済的、社会的、文化的に低い状態に置かれることを強いられ、今なお、日常生活の上で様々な差別を受けるなど、我が国固有の重大な人権問題です。
同和問題の解決を図るため、国や地方公共団体は各種の施策を講じてきましたが、特定の地域出身であることや、そこに住んでいることを理由として、差別的な言動を受けたり、結婚を妨げられるなどの人権侵害が依然として発生しています。
また、かつて、全国の同和地区の地名や所在地等を掲載した図書が販売され、多くの企業が求職者の採否決定等のためにこれを購入していた事実が発覚したことから、採用において公正な選考を進めるための取組が強化されてきました。
しかし、その後も、企業が調査会社に就職希望者の身元調査を依頼したり、同和地区の地名や住所に類すると思われるデータがインターネット上で流布されるなど、差別を助長するような行為は根絶されていません。同和問題の解決に向けて、正しい理解と差別意識の解消のための取組が求められています。
[採用選考のポイント]
採用選考に当たっては、「応募者の基本的人権を尊重すること」「応募者の適性と能力のみを基準とすること」の2点を基本的な考え方として実施することが大切です。
また、本人の意思では変えることのできない事項(本籍や家族の職業等)や、本来自由であるべき事項(思想、信条等)について、質問したり、作文を書かせることは、その意図にかかわらず、就職差別や人権侵害につながる行為です。

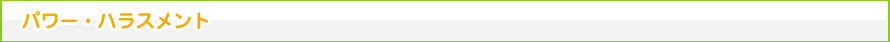
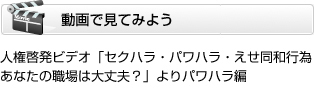
パワー・ハラスメント(パワハラ)は近年登場した造語(和製英語)ですが、現在では社会問題としての認知が進んでいます。 パワー・ハラスメントは、法令上は明確に定義されていません。しかし、一般的には「職場内での地位や権限を利用したいじめ」を指し、「職権等の優位にある権限を背景に、本来の業務範囲を超え、継続的に、相手の人格と尊厳を侵害する言動を行い、就労環境を悪化させる、あるいは雇用不安を与えること」などと言われることもあります。 職場においては、業務を円滑に進めるために、管理職に一定の権限が与えられるとともに、指導の範囲内の注意は、業務上認められています。問題は、権限の遂行そのものではなく、権限をハラスメント(嫌がらせ)に利用することです。業務の範囲を超えた個人の尊厳を不当に傷つけるような言動は、労働環境を悪化させ、働く人の労働意欲を削ぎ、働く権利を侵害する労働問題であるとともに、人権に関わる重大な問題です。
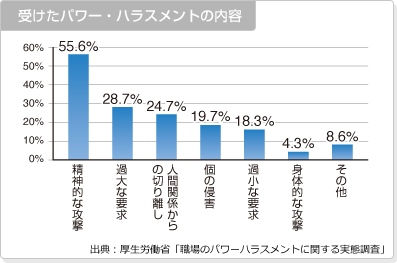
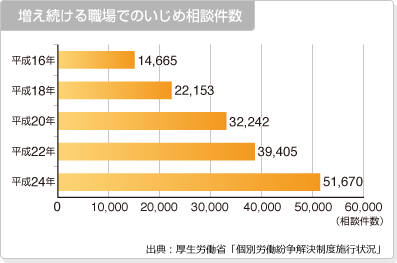
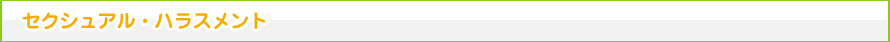
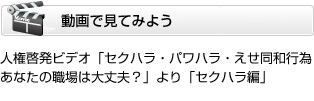
セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)とは、「職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること」とされ、「職務上の地位を利用して、性的な関係を強要する」対価型と、「性的な関係は要求しないが、職場内での性的な言動により働く人たちを不快にさせ、職場環境を損なう」環境型の二つの類型に大別されています。
こうしたセクシュアル・ハラスメントの背景には、尊厳を持った一人の人間ではなく、性的な対象として相手を認識していることが挙げられます。
職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止は、事業主、管理職、従業員といった職務上の立場から考え、それぞれが自らの責任を自覚し、取り組んでいく必要があります。
〔対価型セクシュアル・ハラスメントとは・・・〕
例えば 事業主が性的な関係を要求したが拒否されたので解雇する
人事考課等を条件に性的な関係を求める
職場内での性的な発言に対し抗議した者を配置転換する など
〔環境型セクシュアル・ハラスメントとは・・・〕
例えば 性的な話題をしばしば口にする
宴会で男性に裸踊りをさせる
執ように性的な内容のメールを送る など
平成19年に改正男女雇用機会均等法が施行され、それまで女性労働者に限定されていたセクシュアル・ハラスメント規定が男性労働者にも適用されるようになっています。
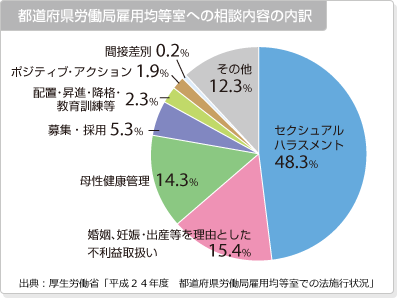
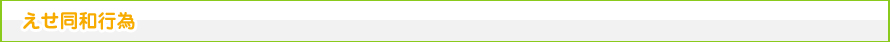
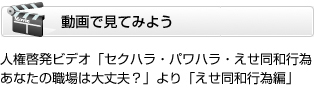
「えせ同和行為」とは、同和問題に対する理解の不足等を口実にして、高額の書籍を売りつけるなど、企業等に不当な利益や義務のないことを要求する行為を言います。こうした行為に対し、その場しのぎに安易な妥協をしたり、恐怖心等から不当な要求に応じる例も見受けられ、えせ同和行為の横行を許す背景となっています。
えせ同和行為は、国民に同和問題に関する誤った意識を植えつける大きな原因となっています。これまで多くの人々が差別解消のために行ってきた活動の努力を踏みにじる行為であり、許されるものではありません。
企業においても、えせ同和行為が及ぼす悪影響を認識し、その排除に取り組む姿勢が求められます。
〔具体的なケース〕
〔対応のポイント〕